来年の戌年にちなむ犬の話
埼玉県の三峰山の三峰神社では、狼が神使とされ「お犬様」と呼ばれる。現在の動物学上のイヌではないが、「いぬ」と呼ばれた動物はいくつかあったようだ。
「狼」とは言葉としては「大神」から来たのだろうが、畏怖すべき動物を別の名で呼ぶことは多く、猪のシシは獣肉の意味、シカは食物の意味と言われるし、鼠を忌物(よめ)と言ったりするのと同様のことなのだろう。
神社の聖域を守る鎮獣である狛犬は、実際はほとんど獅子である。平安時代の御所では獅子と狛犬は区別されていたが、その後民間の寺社では混同されるようになったという。「こまいぬ」とは高麗犬の意味で外国の犬を想像しての名前だという。
中国では「狛」はハクという犬に似た動物の意味だったらしい。ちなみに狗の字もイヌと読むが天狗とは中国では流星のことだったとか。
日本書紀では、海彦山彦の話で、兄の海彦(火酢芹命)が負けて、弟の山彦(彦火火出見尊)の宮を衛ることに奉仕し、狗人(いぬひと)という。その子孫が隼人(はやと)と呼ばれる部族で邪霊を鎮める呪力を有したとされるが、南方の異族の服属儀礼の意味であるともいう。
古事記の雄略天皇の話に、志幾(磯城)の大縣主が天皇の宮殿に似せて家を造ったことが発覚し、布を白い犬にかけて鈴を著けて天皇に献上して詫びたという。犬はやはり服従の意味があるのだろう。天皇はその犬を「つまどひのもの」として若日下部王の家に届け、王を大后とされたという。志幾の大縣主は多くの大后が出た家系だが、意味はよくわからない。
犬は万葉時代から番犬として飼われていた。床を敷いて夫を待つ妻の歌で、訪ねて来た夫に犬よ吠えるなと歌っている。
赤駒を馬屋を建て、黒駒を馬屋を建てて、
そを飼ひ、わが行くが如、思ひ夫(づま) 心に乗りて、
高山の峰のたをりに、射部立てて、鹿猪(しし)待つが如、
床敷きて、わが待つ君を犬な吠えそね(万葉集3278)
犬は産が軽いといい、お産に関する習俗も多い。安産の御守りの犬張り子、戌の日に妊婦が着ける岩田帯、関東近辺に多い村の女性たちによる犬卒塔婆や犬供養など。
歌語り風土記には、犬の伊勢詣り、犬頭糸伝説などもある。
「狼」とは言葉としては「大神」から来たのだろうが、畏怖すべき動物を別の名で呼ぶことは多く、猪のシシは獣肉の意味、シカは食物の意味と言われるし、鼠を忌物(よめ)と言ったりするのと同様のことなのだろう。
神社の聖域を守る鎮獣である狛犬は、実際はほとんど獅子である。平安時代の御所では獅子と狛犬は区別されていたが、その後民間の寺社では混同されるようになったという。「こまいぬ」とは高麗犬の意味で外国の犬を想像しての名前だという。
中国では「狛」はハクという犬に似た動物の意味だったらしい。ちなみに狗の字もイヌと読むが天狗とは中国では流星のことだったとか。
日本書紀では、海彦山彦の話で、兄の海彦(火酢芹命)が負けて、弟の山彦(彦火火出見尊)の宮を衛ることに奉仕し、狗人(いぬひと)という。その子孫が隼人(はやと)と呼ばれる部族で邪霊を鎮める呪力を有したとされるが、南方の異族の服属儀礼の意味であるともいう。
古事記の雄略天皇の話に、志幾(磯城)の大縣主が天皇の宮殿に似せて家を造ったことが発覚し、布を白い犬にかけて鈴を著けて天皇に献上して詫びたという。犬はやはり服従の意味があるのだろう。天皇はその犬を「つまどひのもの」として若日下部王の家に届け、王を大后とされたという。志幾の大縣主は多くの大后が出た家系だが、意味はよくわからない。
犬は万葉時代から番犬として飼われていた。床を敷いて夫を待つ妻の歌で、訪ねて来た夫に犬よ吠えるなと歌っている。
赤駒を馬屋を建て、黒駒を馬屋を建てて、
そを飼ひ、わが行くが如、思ひ夫(づま) 心に乗りて、
高山の峰のたをりに、射部立てて、鹿猪(しし)待つが如、
床敷きて、わが待つ君を犬な吠えそね(万葉集3278)
犬は産が軽いといい、お産に関する習俗も多い。安産の御守りの犬張り子、戌の日に妊婦が着ける岩田帯、関東近辺に多い村の女性たちによる犬卒塔婆や犬供養など。
歌語り風土記には、犬の伊勢詣り、犬頭糸伝説などもある。
 今日は冬至だった。年末年始は季節の行事の話題が多くなると思う。
今日は冬至だった。年末年始は季節の行事の話題が多くなると思う。
 元禄15年の今日、12月14日は、赤穂浪士、四十七士の討ち入りのあった日である。
元禄15年の今日、12月14日は、赤穂浪士、四十七士の討ち入りのあった日である。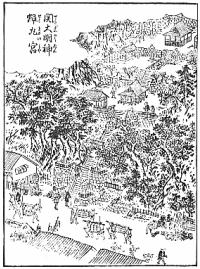 京都にいちばん近い関所は、近江国へ抜ける逢坂(オウサカ)の関である。平安時代の初めここには盲目の琵琶法師、蝉丸が住んでいたという。百人一首に歌がある。
京都にいちばん近い関所は、近江国へ抜ける逢坂(オウサカ)の関である。平安時代の初めここには盲目の琵琶法師、蝉丸が住んでいたという。百人一首に歌がある。