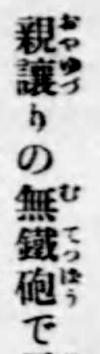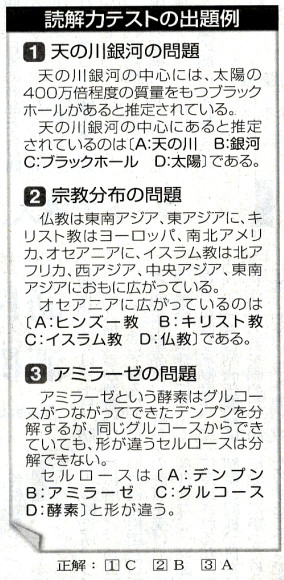「用ゐる」の仮名遣ひ表記について
「用ゐる」の仮名遣ひ表記について、気になることがあったので、辞書(シャープ電子辞書)を引いてみた。
電子辞書は「ゐ」が打てないので「もちい」とキーボードから指定。
最初に「用ゆ」(ヤ行上二段)の項が出た。「もちい」で検索したからだろう。
用例に宇治拾遺物語からの引用がある。
しかし説明に、「『もちゐる』に同じ」と書かれるので、「→用ゐる[参考]」の部分をクリック。すると……
「用ゐる」(ワ行上一段)の項が出た。
用例は徒然草や源氏物語など多数。説明文は、かなり長い。本来ならこちらを最初に表示すべきところだが、キーボード入力のときに「ゐ」が使えず、「もちい」としたため、ヤ行が優先されたのであらう。電子辞書には旺文社「全訳古語辞典」が収録されてゐるが、「ゐ」や「ゑ」を使へないので、実に不便なのである。
その「用ゐる」についての説明によると、後世ハ行上二段「もちふ」、ヤ行上二段「もちゆ」と誤用される例も生まれた、といふ。前述の宇治拾遺物語は、誤用だったことになる。
「もちゐる」は「持ち・率(ゐ)る」の意とも書かれ、これは事前に想像した通りの語源説である。
「もちふ」を同辞書で調べてみると、「もちいる」に同じとあり、("もちふ"の)説明は短いが、用例は源氏物語からである。源氏物語では「用ゐる」と「用ふ」の2つが使用されてゐることになる。書写した人が違うためかもしれない。
「もちゐる」は「持ち+率る」と解釈できるわけでが、では
「もちふ」は「持ち+ふ」となり、「ふ」とは何であらうかといふことになる。やはり誤用なのだらう。
「もちゆ」も「持ち+ゆ」となり、「ゆ」とは何か。これも不明である。
下二段活用なので連用形は「もちいる」となり、語の途中に母音の「い」が入るといふのは、万葉集など上代では安定しない語形である。「這ひ入る」→「はひる」と変る語もある。万葉集には「もちいる」はないので、それは後世の誤用なのだらう。
ところで、平安時代末期の藤原定家の時代には、「ゐ」と「い」、「ゑ」と「え」の発音の区別がなくなり、独自の「定家仮名遣ひ」が考案されたといふ。平安中期の源氏物語の時代には、発音の通りに「ゐ」と「ゑ」を書き分ければ、それが今でいふ歴史的仮名遣ひになったわけだが、平安末期以後はそうはならない。そこで仮名遣ひの法則を覚えて書き分けなければならなくなったわけだ。
「誤用」といふ言葉を広義に解せば、定家仮名遣ひの中にも「誤用」は多くあるはずであり、冒頭の宇治拾遺物語についても同様。
古典に使用例があるからといって、あれもこれも許容していったら、際限がなくなる。
江戸時代の木版本の表記まで含めたら、仮名遣ひは無いに等しいものとなってしまふ。
電子辞書は「ゐ」が打てないので「もちい」とキーボードから指定。
最初に「用ゆ」(ヤ行上二段)の項が出た。「もちい」で検索したからだろう。
用例に宇治拾遺物語からの引用がある。
しかし説明に、「『もちゐる』に同じ」と書かれるので、「→用ゐる[参考]」の部分をクリック。すると……
「用ゐる」(ワ行上一段)の項が出た。
用例は徒然草や源氏物語など多数。説明文は、かなり長い。本来ならこちらを最初に表示すべきところだが、キーボード入力のときに「ゐ」が使えず、「もちい」としたため、ヤ行が優先されたのであらう。電子辞書には旺文社「全訳古語辞典」が収録されてゐるが、「ゐ」や「ゑ」を使へないので、実に不便なのである。
その「用ゐる」についての説明によると、後世ハ行上二段「もちふ」、ヤ行上二段「もちゆ」と誤用される例も生まれた、といふ。前述の宇治拾遺物語は、誤用だったことになる。
「もちゐる」は「持ち・率(ゐ)る」の意とも書かれ、これは事前に想像した通りの語源説である。
「もちふ」を同辞書で調べてみると、「もちいる」に同じとあり、("もちふ"の)説明は短いが、用例は源氏物語からである。源氏物語では「用ゐる」と「用ふ」の2つが使用されてゐることになる。書写した人が違うためかもしれない。
「もちゐる」は「持ち+率る」と解釈できるわけでが、では
「もちふ」は「持ち+ふ」となり、「ふ」とは何であらうかといふことになる。やはり誤用なのだらう。
「もちゆ」も「持ち+ゆ」となり、「ゆ」とは何か。これも不明である。
下二段活用なので連用形は「もちいる」となり、語の途中に母音の「い」が入るといふのは、万葉集など上代では安定しない語形である。「這ひ入る」→「はひる」と変る語もある。万葉集には「もちいる」はないので、それは後世の誤用なのだらう。
ところで、平安時代末期の藤原定家の時代には、「ゐ」と「い」、「ゑ」と「え」の発音の区別がなくなり、独自の「定家仮名遣ひ」が考案されたといふ。平安中期の源氏物語の時代には、発音の通りに「ゐ」と「ゑ」を書き分ければ、それが今でいふ歴史的仮名遣ひになったわけだが、平安末期以後はそうはならない。そこで仮名遣ひの法則を覚えて書き分けなければならなくなったわけだ。
「誤用」といふ言葉を広義に解せば、定家仮名遣ひの中にも「誤用」は多くあるはずであり、冒頭の宇治拾遺物語についても同様。
古典に使用例があるからといって、あれもこれも許容していったら、際限がなくなる。
江戸時代の木版本の表記まで含めたら、仮名遣ひは無いに等しいものとなってしまふ。
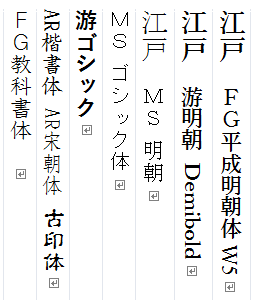 W5 Demibold は太字のこと。
W5 Demibold は太字のこと。