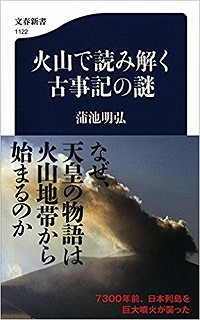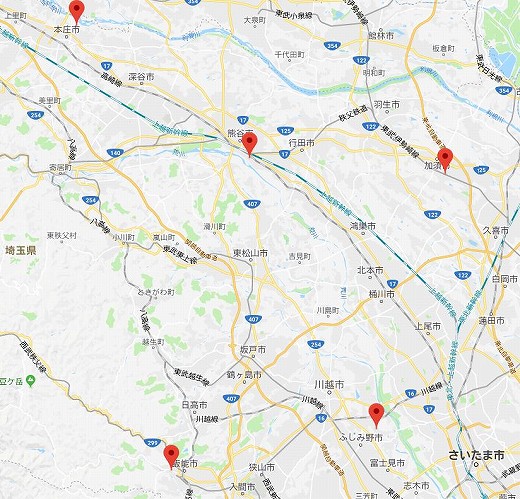海幸彦と山幸彦
農村向けの雑誌『家の光』の付録に『こども家の光』という小さい冊子が毎月付いていたころがあり、昭和31年6月号に、古事記の神話物語「海幸彦山幸彦の物語」が載ってゐた。浜田広介の執筆。画像は4ページのうちの2ページ。

古事記の物語と大きく異なる部分がある。
ここでの海幸彦山幸彦は高天原に住んでゐることになってゐるが、古事記では日向国である。意図は不明。
釣道具と弓矢の交換を提案したのは、古事記では弟の山幸彦である。山幸彦は自分で言ひ出して兄の釣り針を紛失したが、それで最後に兄を懲らしめるのでは、少々正義から遠くなるといふ理解なのかもしれない。
3ページ目以後の話では、綿津見宮の井戸で水を汲んでゐたのは、古事記では豊玉姫ではなくその従婢である。しかしこの場面は他の多くの作家による再話でも、豊玉姫と山幸彦の直接の出会ひに脚色されてゐる。そのほうがラブロマンスとしてドラマチックなのだらう。しかし子供向けなのでロマンスは省略されてゐる。
古事記では、山幸彦は綿津見宮で三年もの間、接待を受けて、釣り針のことを忘れてゐたのだが、この再話では釣り針はすぐに見つかる。全体の話を短くまとめるためだらうか。

「こども家の光」には、日本の古い話が多く掲載されてゐたかといふと、そうでもなく、毎月、世界の童話などが少しづつ遍ねく紹介され、そのうちの一つといふこと。(2017.08.10)

古事記の物語と大きく異なる部分がある。
ここでの海幸彦山幸彦は高天原に住んでゐることになってゐるが、古事記では日向国である。意図は不明。
釣道具と弓矢の交換を提案したのは、古事記では弟の山幸彦である。山幸彦は自分で言ひ出して兄の釣り針を紛失したが、それで最後に兄を懲らしめるのでは、少々正義から遠くなるといふ理解なのかもしれない。
3ページ目以後の話では、綿津見宮の井戸で水を汲んでゐたのは、古事記では豊玉姫ではなくその従婢である。しかしこの場面は他の多くの作家による再話でも、豊玉姫と山幸彦の直接の出会ひに脚色されてゐる。そのほうがラブロマンスとしてドラマチックなのだらう。しかし子供向けなのでロマンスは省略されてゐる。
古事記では、山幸彦は綿津見宮で三年もの間、接待を受けて、釣り針のことを忘れてゐたのだが、この再話では釣り針はすぐに見つかる。全体の話を短くまとめるためだらうか。

「こども家の光」には、日本の古い話が多く掲載されてゐたかといふと、そうでもなく、毎月、世界の童話などが少しづつ遍ねく紹介され、そのうちの一つといふこと。(2017.08.10)