統一教会の問題
1970年代後半ごろの統一教会は、各大学で原理研究会、聖書研究会なるサークルを作り、勧誘した学生たちを一日中ビデオ漬けにして洗脳するというものだった。
家庭用VHSデッキが発売されたのが、1976年のことで、値段は20万円以上だったらしいが、金のある組織が、時代の最先端機器を利用したことになる。
「映画は受動的に観るだけで頭を使わず、脳に良くない」というのは、世界一知能指数の高いとされる女性の言葉だが、なるほど一理はあるであろう。洗脳には打って付けの道具になる。
今回の狙撃犯は、安倍首相のビデオメッセージを何度も見て怒りを募らせたのであろう。そうした効果もあるのだろう。
その後、1980年代のバブル経済のころは、統一教会による霊感商法なるものが騒がれた。世間では土地投企などが蔓延し、土地を売れば高額な現金収入になった時代でもあった。
90年代は、有名芸能人が参加した合同結婚式で騒がれた。形式の異様さとともに、教団自らが、教祖の初夜権の名残りであることを示唆するような説明をしていたのには驚いた。教団の源流となった団体が、元々いかがわしいものだったらしく、近代父権制イデオロギーに偏重した結婚思想は、後の選択的夫婦別姓反対やマイノリティ差別と同根とみて間違いない。
自民党の議員秘書の多くは、統一教会からの派遣であるとは、90年代からいわれていた。教団員である秘書が、関連団体のイベントに際して祝電を打つのなら手慣れたものである。秘書が関連団体だとは知らなかったということはありえない。
00年代はマスコミで騒がれることが少なくなったが、最近の報道によると、2012年ごろから、教団は新たな問題を拡大させてきたようだ。
2012年に教祖の文鮮明が死に、分派のようなものができているらしい。といっても分派が独立の宗教法人として認可を受けているとは思われず、上納金を競っている程度ではないだろうか。上納金が多ければ、教団内での地位が上がるのだろう。上納金だけでなく、与党への浸透度についても競ってきたのだろう。2012年は2次安倍政権である。
土地を売れば手軽に現金収入になる時代ではなくなったが、どこかにアブク銭はあるのだろう。政治がらみの銭もその一種かもしれない。
90年代以前は、入信者になった者を周囲がカルト教団から引き離すことに努力してきたが、信者の二世問題という複雑な問題があることもわかってきた。
(中略)
日本人は何事も常に性善説で対応してきたことが多かったのではないかと思う。特に海外からのものに対して無批判的に受け入れることによって短期間での経済繁栄を成功させた体験もある。グローバル社会の中では、それでは日本自身を滅ぼすことになることを、学ばねばならなくなるような気がする。
目的と手段の問題。目的のために手段を選ばない者たち。
目的は当事者が正しいと思っていれば良いわけではなく、手段のありかたによって目的の正しさが保証されるものであるということ。
家庭用VHSデッキが発売されたのが、1976年のことで、値段は20万円以上だったらしいが、金のある組織が、時代の最先端機器を利用したことになる。
「映画は受動的に観るだけで頭を使わず、脳に良くない」というのは、世界一知能指数の高いとされる女性の言葉だが、なるほど一理はあるであろう。洗脳には打って付けの道具になる。
今回の狙撃犯は、安倍首相のビデオメッセージを何度も見て怒りを募らせたのであろう。そうした効果もあるのだろう。
その後、1980年代のバブル経済のころは、統一教会による霊感商法なるものが騒がれた。世間では土地投企などが蔓延し、土地を売れば高額な現金収入になった時代でもあった。
90年代は、有名芸能人が参加した合同結婚式で騒がれた。形式の異様さとともに、教団自らが、教祖の初夜権の名残りであることを示唆するような説明をしていたのには驚いた。教団の源流となった団体が、元々いかがわしいものだったらしく、近代父権制イデオロギーに偏重した結婚思想は、後の選択的夫婦別姓反対やマイノリティ差別と同根とみて間違いない。
自民党の議員秘書の多くは、統一教会からの派遣であるとは、90年代からいわれていた。教団員である秘書が、関連団体のイベントに際して祝電を打つのなら手慣れたものである。秘書が関連団体だとは知らなかったということはありえない。
00年代はマスコミで騒がれることが少なくなったが、最近の報道によると、2012年ごろから、教団は新たな問題を拡大させてきたようだ。
2012年に教祖の文鮮明が死に、分派のようなものができているらしい。といっても分派が独立の宗教法人として認可を受けているとは思われず、上納金を競っている程度ではないだろうか。上納金が多ければ、教団内での地位が上がるのだろう。上納金だけでなく、与党への浸透度についても競ってきたのだろう。2012年は2次安倍政権である。
土地を売れば手軽に現金収入になる時代ではなくなったが、どこかにアブク銭はあるのだろう。政治がらみの銭もその一種かもしれない。
90年代以前は、入信者になった者を周囲がカルト教団から引き離すことに努力してきたが、信者の二世問題という複雑な問題があることもわかってきた。
(中略)
日本人は何事も常に性善説で対応してきたことが多かったのではないかと思う。特に海外からのものに対して無批判的に受け入れることによって短期間での経済繁栄を成功させた体験もある。グローバル社会の中では、それでは日本自身を滅ぼすことになることを、学ばねばならなくなるような気がする。
目的と手段の問題。目的のために手段を選ばない者たち。
目的は当事者が正しいと思っていれば良いわけではなく、手段のありかたによって目的の正しさが保証されるものであるということ。
 『血の歌』は、作詞家でもある なかにし礼の小説で、没後に発表された。
『血の歌』は、作詞家でもある なかにし礼の小説で、没後に発表された。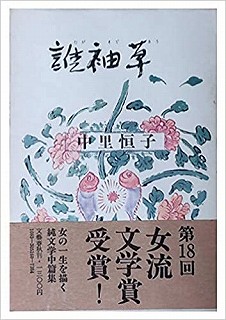
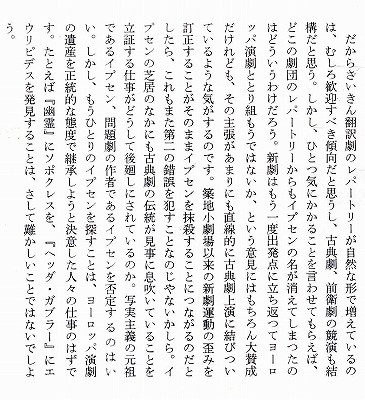
 「幕末の三舟」とは勝海舟、山岡鉄舟、高橋泥舟のことだが、高橋泥舟はあまり表立ったことは好まなかったらしい。
「幕末の三舟」とは勝海舟、山岡鉄舟、高橋泥舟のことだが、高橋泥舟はあまり表立ったことは好まなかったらしい。