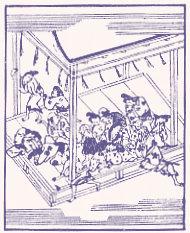
井原西鶴の『好色一代男』などには、ときどき折々の年中行事や民俗、地方の神々のことも書かれていて、興味深い。江戸時代初期のものだが、そういった庶民の信仰は戦後まもなくのころまでほとんど変わらず続いて来たことのように思える。
それらを本から拾い出して主人公の名をとって『世之介歳時記』としてまとめると面白いと思うが、少しだけ試みてみる。
最初は別の本で『本朝桜陰比事』から。
「昔、京都の町に高家の御吉例を勤める年男があった。毎年12月21日にきまって丹波境の村里から山奥のほうへ分け入って、正月の門松を伐る習わしになっていた。……ここは昔から飾山といって門松を伐るところに決まっていた……」(麻生磯次訳以下同じ)
年末に年男が山から松の木を伐って来て、正月の門松とし、他にも正月の準備をするわけである。
「さすがに元旦の陽ざしは静かにゆったりとして、世に時めく人たちの門には、松の緑も濃く、「物申、物申」という年始客の声が絶えない。手毯もつけば羽根もつく、その羽子板の絵に、夫婦子供の絵のかいてあるのも羨しく、懸想文を買って読む女には男が珍しく思われ、暦の読み初めに「姫始め」とあるのもおもしろい。人の心も浮き立って、昨日の大晦日の苦しかったことも忘れて、今日の一日も暮れてしまう。」
元旦は年始まわりである(初詣は明治以降の習俗)。懸想文とは今でいうと恋占いのおみくじのようなもので、現代もあまり変わっていない。「男が珍しく思われ」とは、まだそんな年頃でもないのにといった意味だろうと思う。
「二日は年越だというので、人に誘われて鞍馬山に出かけた。市原野を行くと、厄払いの声がし、夢違いの獏の札や宝舟などを売る声が聞え、家々では鰯・柊を軒にさし、鬼やらいの豆撒きをして、門口は宵のうちから固くとざしていた。懸金という坂を上って、鞍馬寺の鰐口の紐にすがって鳴らそうとする拍子に、柔かな女の手に触れると、早くも恋の種が芽生え出した。むかし、扇の女房絵を見て恋い慕い、この寺に参籠した男のことや、
物思へば沢の螢もわが身よりあくがれ出づる玉かとぞ見る
と詠んだ女のことまでも思い出されて、そぞろに心も浮き立った折から、鶏の鳴き声をまねる者があったので、目を覚まして人々はみな帰ることになった。」
旧暦なので新年と節分がほぼ同時に来るわけである。現代では新年の行事と節分の行事ははっきり区別できるが、これを読むと両方がごっちゃになってわかりにくいところもある。初夢の宝船売りは、この時代は節分の行事だったらしい。
「物思へば沢の螢も」の歌は、和泉式部が鞍馬寺の先の貴船神社に参詣したとき詠まれたもので、夫婦の復縁を祈った歌という。
「その年十四の春も過ぎて、衣替えする四月ついたちから、振袖の脇を塞いで詰袖を着ることになったが、もうしばらく振袖姿にしておきたいと、世間の人々から惜しまれたのも、後姿がいかにもよかったからである。
……村の子供たちは、麦藁でねじ籠や雨蛙の家などを作って遊んでいる」
「詰め袖」は元服後の成人の服装のことだが、世之介は美少年だったので、少年時代の振袖姿が惜しまれたようだ。
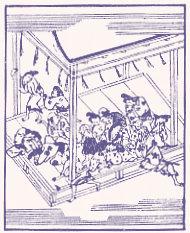 井原西鶴の『好色一代男』などには、ときどき折々の年中行事や民俗、地方の神々のことも書かれていて、興味深い。江戸時代初期のものだが、そういった庶民の信仰は戦後まもなくのころまでほとんど変わらず続いて来たことのように思える。
井原西鶴の『好色一代男』などには、ときどき折々の年中行事や民俗、地方の神々のことも書かれていて、興味深い。江戸時代初期のものだが、そういった庶民の信仰は戦後まもなくのころまでほとんど変わらず続いて来たことのように思える。 鯉のぼりを上げる風習は、古い記録では江戸時代のものがあるらしい。
鯉のぼりを上げる風習は、古い記録では江戸時代のものがあるらしい。 北国をのぞけば日本の桜の時期ももう終りである。
北国をのぞけば日本の桜の時期ももう終りである。