音楽脳
秋の夜に聴く虫の声は、日本人にとっては耳に心地良いものだが、西洋人にとっては雑音にしか聞えないという話は、一般にも知られていると思う。
角田忠信氏によると、人の左脳と右脳の使い方が、日本人と西欧人で異なることが原因で、そうなるらしい。
人間の脳は、左脳と右脳で役割が異なり、左脳は、おもに言語や計算を担当し、言語脳ともいう、右脳は言語以外の音楽や自然音、雑音などを担当するので非言語脳または音楽脳ということがある。
では、言葉と音楽と、両方が混ざった音は、どうなるかというと、言語が優位になるので、言語脳(左脳)だけで処理されるという。このとき言語脳は雑音を選り分けしながら処理するので、疲労感が残るのだとか。、
鳥の声や虫の声は、どちらの脳が受け持つかというと、西欧人にとっては自然音なので右脳。日本人は言語と同じように左脳になる、という大きな違いがあるそうだ。日本人が鳥や虫の声に情緒を感じるのは、言語と同じ左脳処理が原因ではないかというのである。(右脳・芸術脳でなく)
室内でオーケストラの器楽曲の音楽を聞きながら、窓の外から鳥の声が聞えたりすると、聴衆はなぜか音楽に集中できなくなっていた、という音楽評論家の吉田秀和の著書からの紹介がある。これも、日本人は鳥の声も人間の声も同じように聞くためだという。
以上は、角田忠信著『日本人の脳』という本からのごく一部が『エッセイおとなの時間・遊びなのか学問か』(新潮社)に掲載され、それを読んで感心したわけである。これらは、10歳くらいまでに日本語を母国語として習得した人に当てはまるという。
そこで同書を取り寄せて他の部分も読んでみた。
中国人や朝鮮人は、西洋人と同様であり、日本人やポリネシア人など世界でもごく一部だけでだけがそのような耳ををもつらしい。
日本人は、鳥や動物の声の他に、川のせせらぎの音、風の音も、左脳で聞くというから、情緒を込めて聞いているわけである。
さらに日本の笛や三味線などの和楽器の音も、左脳が優位になるという。洋楽器は右脳。
西洋人は、人の声のハミング、母音を伸ばした声なども、右脳が優位だが、日本人は左脳だという。
匂いについても、西洋人なら右脳優位だが、日本人なら左脳になるものに、花、果物、化粧品の匂い。タバコや焼け焦げの匂い、体臭などの悪臭、などがある。
著者は、日本人は左脳を使いすぎるので、もっと右脳を使うべきで、クラシック音楽の器楽曲などが良いなどの提案している。
ただし匂いのある「タバコは想像活動を阻害する」というのだが、左脳優位がいけないというのなら、花の香も、水のせせらぎも、鳥の声も、日本的な花鳥風月に関する全て排除せよということになり、このタバコ排除の提案は間違いだろう。
ところで、日本人全てがこの傾向にあるのではなく、7%は左右が逆であり、22%は左脳右脳どちらかの優位をはっきり示さないという。残りの70%ちょっとについてだけ該当するのがこの話らしい。これでは、自分はそのうちのどれに該当するのだろうかという話になってくる。右脳の活用も良いが、70%に入らない小数派の日本人を尊重すべきだという考えもありうると思う。
とはいえ、日本語や音楽の研究にとっては、これらは重要な発見であろう。
西洋人が、言葉の子音と短母音だけを左脳優位で認識するのは、強弱アクセントと関係があるのではないだろうか。強弱アクセントは間違えば意味が通じないので注意して聞くと思うが、長母音はいくら長く伸ばしても意味は変らないので右脳でよいということかもしれない。
日本語では音の強弱には意味はない。音の高低についても、たとえば「ムギ、ハタケ」と言う音の高低は「ムギバタケ」と続けて言うときに変わってしまう。日本語では音の高低を間違ってもかなり通じるだろう。かなで書くと同じになる箸と橋の間違いは通じにくいだろうが、文脈からの類推で通じることもある。それは言葉の全てを注意をはらいながら左脳で聞いているからということになる。
日本の歌謡曲では、長母音の途中で強弱等をつけるコブシという唱法があるが、日本語の強弱には言語的な意味はないために歌い手の気分で自由にできるのだろう。長音の途中でビブラートを強める日本人歌手も少なくない。しかし音の途中で強弱が入ると別の音の始りかと感じてしまうせいか、非常に聞きづらく思う今日このごろである。
角田忠信氏によると、人の左脳と右脳の使い方が、日本人と西欧人で異なることが原因で、そうなるらしい。
人間の脳は、左脳と右脳で役割が異なり、左脳は、おもに言語や計算を担当し、言語脳ともいう、右脳は言語以外の音楽や自然音、雑音などを担当するので非言語脳または音楽脳ということがある。
では、言葉と音楽と、両方が混ざった音は、どうなるかというと、言語が優位になるので、言語脳(左脳)だけで処理されるという。このとき言語脳は雑音を選り分けしながら処理するので、疲労感が残るのだとか。、
鳥の声や虫の声は、どちらの脳が受け持つかというと、西欧人にとっては自然音なので右脳。日本人は言語と同じように左脳になる、という大きな違いがあるそうだ。日本人が鳥や虫の声に情緒を感じるのは、言語と同じ左脳処理が原因ではないかというのである。(右脳・芸術脳でなく)
室内でオーケストラの器楽曲の音楽を聞きながら、窓の外から鳥の声が聞えたりすると、聴衆はなぜか音楽に集中できなくなっていた、という音楽評論家の吉田秀和の著書からの紹介がある。これも、日本人は鳥の声も人間の声も同じように聞くためだという。
以上は、角田忠信著『日本人の脳』という本からのごく一部が『エッセイおとなの時間・遊びなのか学問か』(新潮社)に掲載され、それを読んで感心したわけである。これらは、10歳くらいまでに日本語を母国語として習得した人に当てはまるという。
そこで同書を取り寄せて他の部分も読んでみた。
中国人や朝鮮人は、西洋人と同様であり、日本人やポリネシア人など世界でもごく一部だけでだけがそのような耳ををもつらしい。
日本人は、鳥や動物の声の他に、川のせせらぎの音、風の音も、左脳で聞くというから、情緒を込めて聞いているわけである。
さらに日本の笛や三味線などの和楽器の音も、左脳が優位になるという。洋楽器は右脳。
西洋人は、人の声のハミング、母音を伸ばした声なども、右脳が優位だが、日本人は左脳だという。
匂いについても、西洋人なら右脳優位だが、日本人なら左脳になるものに、花、果物、化粧品の匂い。タバコや焼け焦げの匂い、体臭などの悪臭、などがある。
著者は、日本人は左脳を使いすぎるので、もっと右脳を使うべきで、クラシック音楽の器楽曲などが良いなどの提案している。
ただし匂いのある「タバコは想像活動を阻害する」というのだが、左脳優位がいけないというのなら、花の香も、水のせせらぎも、鳥の声も、日本的な花鳥風月に関する全て排除せよということになり、このタバコ排除の提案は間違いだろう。
ところで、日本人全てがこの傾向にあるのではなく、7%は左右が逆であり、22%は左脳右脳どちらかの優位をはっきり示さないという。残りの70%ちょっとについてだけ該当するのがこの話らしい。これでは、自分はそのうちのどれに該当するのだろうかという話になってくる。右脳の活用も良いが、70%に入らない小数派の日本人を尊重すべきだという考えもありうると思う。
とはいえ、日本語や音楽の研究にとっては、これらは重要な発見であろう。
西洋人が、言葉の子音と短母音だけを左脳優位で認識するのは、強弱アクセントと関係があるのではないだろうか。強弱アクセントは間違えば意味が通じないので注意して聞くと思うが、長母音はいくら長く伸ばしても意味は変らないので右脳でよいということかもしれない。
日本語では音の強弱には意味はない。音の高低についても、たとえば「ムギ、ハタケ」と言う音の高低は「ムギバタケ」と続けて言うときに変わってしまう。日本語では音の高低を間違ってもかなり通じるだろう。かなで書くと同じになる箸と橋の間違いは通じにくいだろうが、文脈からの類推で通じることもある。それは言葉の全てを注意をはらいながら左脳で聞いているからということになる。
日本の歌謡曲では、長母音の途中で強弱等をつけるコブシという唱法があるが、日本語の強弱には言語的な意味はないために歌い手の気分で自由にできるのだろう。長音の途中でビブラートを強める日本人歌手も少なくない。しかし音の途中で強弱が入ると別の音の始りかと感じてしまうせいか、非常に聞きづらく思う今日このごろである。
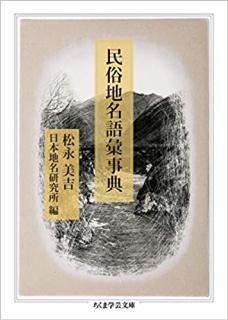 民俗地名語彙事典 松本美吉、ちくま文庫
民俗地名語彙事典 松本美吉、ちくま文庫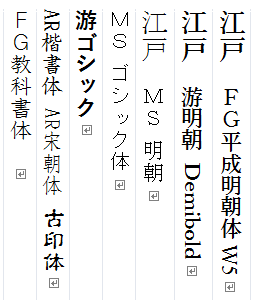 W5 Demibold は太字のこと。
W5 Demibold は太字のこと。 『日本人の生活全集7 〜日本人の芸能』(池田弥三郎著、岩崎書店 1957)なる本を入手。
『日本人の生活全集7 〜日本人の芸能』(池田弥三郎著、岩崎書店 1957)なる本を入手。


