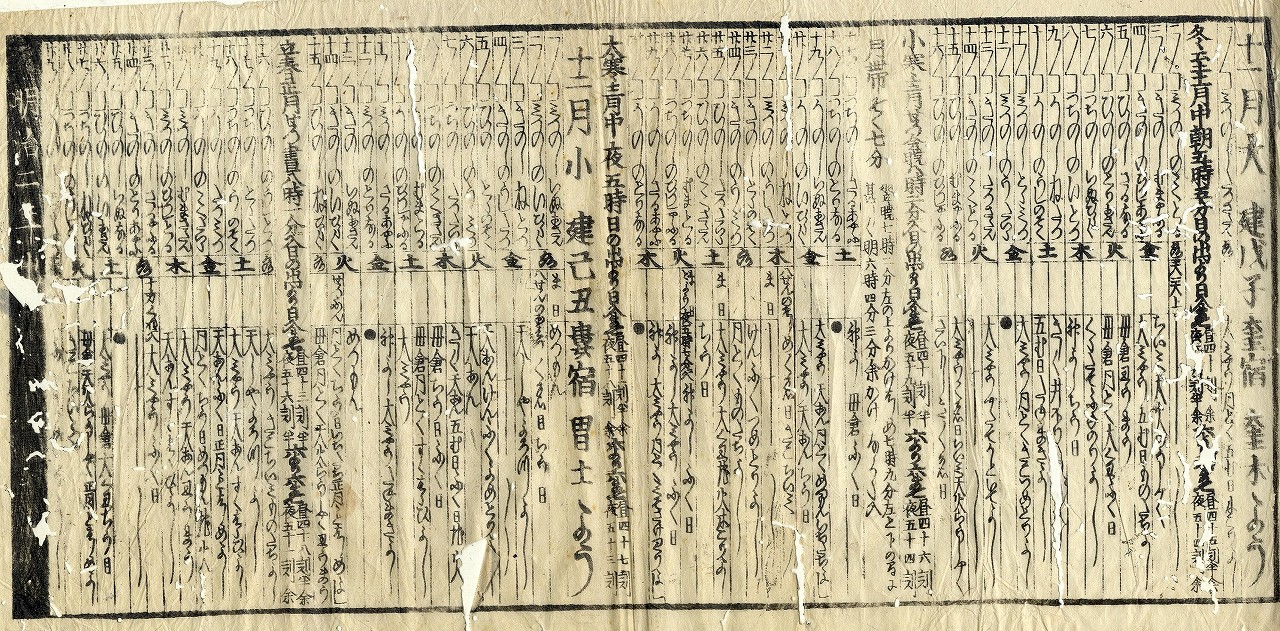誰袖草
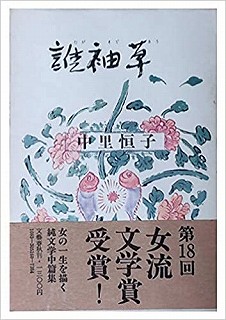
久しぶりに小説を読んだ。中里恒子の『誰袖草(たがそでそう)』。
「読んでみたいと思っていた小説の条件」を、いくつか満たしていた。
条件の1つは、古典の本歌取りのようなところ。
誰袖草とは、古今集の「色よりも香こそあはれとおもほゆれ誰が袖触れし宿の梅ぞも」という歌にちなむ名前の植物らしい。匂い袋のことを誰袖ともいうとのこと。
そして、中将姫伝説を追いかけるような物語になっていて、折口信夫の『死者の書』の話も出てくる。
2つめには、明治大正時代の人たちの生活慣習の一部にリアリティがあったこと。大店の女性たちの生活の一部に限ってのことではあるが。
3つめには、夫が愛人を妊娠させ、生れてくる子を妻の実子として全てをとりつくろうというトリッキーな計画があり、どのように運ぶのだろうと詳細を注目して読んだ。しかし流産やら関東大震災の直撃やらで、偽装する必要はなくなるのであるが。
突然の大震災の話には、読んでいて困惑。人物たちは日を追って立ち直ってゆくのだが、読み手にはまだ30分程度しか経過せず、読むのを中断して、続きは明日読もうということになった。
同じ本に、『置き文』という中編も収録。
こちらは舞台は隠岐で、隠岐へ流された後鳥羽上皇の話や、御製歌などが多く出てくる。
隠岐へ嫁いで、娘を設けた女性が、20年後に娘へ宛てた置き文を残して家出をする。
母の名はアキ(飽き?)で、娘の名はユキ。
島を訪れた植物学者の男に、娘は初恋ともいえない憧れを抱いていたが、母は年下のその男と逃げたのである。
男はキノコなどを研究する学者。20年に一度だけこの世のどこかに発生するキノコがあるという。それは毒キノコなのかどうかはわからないが、20年後の母の恋にもかさなる。
本の一作目が誰袖草という植物の名前なので、この小説の題名もキノコの名前にしたらどうだろうと思ったが、毒々しくてもいけないのかもしれない。
母が島を脱出するときは、周囲に気づかれないトリッキーな方法で行なっている。この方法なら自然に成功するのだろうと思えたが、前作のような自分が生んでいない子を生んだことにするようなこと……というのは江戸時代なら周囲が事情を察してその件は口を閉ざせばよいだけの話かもしれないが、明治大正期では、「誰袖草」で途中まで試みられたようなこともあったのであろう。